ギター・ベースの製造販売を手掛ける株式会社ラムトリックカンパニー(埼玉・川口)取締役社長の竹田豊氏に取材を実施。会社の歴史やギター製造におけるこだわり、そして社長が考える「ハレノヒ」についてお話を伺いました
(聞き手:ハレノヒハレ 大塚辰徳 編集:ライフメディア 岸のぞみ)
ピンの取り付け1つにもこだわるオーダーメード楽器
まずは御社の事業内容について改めて簡単にお聞かせください。
竹田 豊氏(以下、竹田氏):「Sonic」というブランドでギター・ベースの製造販売を手掛けています。ギターやベースは、その都度仕様を決定して製作するオーダーメード。派手な広告を打ってアピールすることはありませんが、当たり前のことを当たり前にやることを重視してきました。演奏者にいかに気持ちよく楽器を弾いてもらえるかに主眼を置いた、アーティストに寄り添う楽器の製作を得意としています。
会社設立以来、楽器の製作とともに延べ6000本以上に及ぶ楽器の修理も手掛けてきました。以前はクライアントの希望に沿った修理をしていましたが、それだと自分的に納得の行かない部分を残したまま楽器を返さなければならないことが多いため、2000年頃から他社製の楽器については「はずせる部品は全部はずして、弊社基準で再組立する」Tune-upというメニューでしか修理は受け付けないことにしました。

Sonicブランドの具体的なこだわりはどのような点にありますか?
竹田氏:ネジ、ブリッジ、ピックアップなど、こだわらない部分がないんです。トラディショナルなスタイルの中で極限までいい楽器に仕上げるのが私たちの仕事です。
例えばストラップピン。ギターのボディには楽器を肩からかけるためのストラップをつなぐストラップピンが取り付けられています。しかし機種によっては取付部がカーブのきつい曲面になっており、その頂点に底面が平らなストラップピンをつけると両端が浮いて、接触する面が頂上だけになってしまいますよね。見た目にも違和感がありますし、ピンも緩みやすくなります。
そこであらかじめ取り付け部分に平らな面を作っておくことでストラップをつけた際にもネジが緩みにくく、見た目も綺麗に仕上げる仕様に変更しました。この工程を入れるためだけに専用の工具も作りました。このようなこだわりはあらゆる箇所にあるんですよ。
楽器製造における竹田社長の哲学についてもお聞かせください。
竹田氏:既存のスタイルの中でいいものをつくる。これに尽きます。ストラップピンのこだわりを始めたのは20年ほど前からですが、ごく最近になってこだわり始めたところもたくさんあります。ずっと楽器と向き合っていると、今までこれが当たり前だったけれど、なんでこの部分はこうするんだろう? と疑問を覚えることがたくさんあるんです。もっとこうしたほうがいいんじゃないか? もっとここを変えれば演奏者が気持ちいいんじゃないか。
昨日作った楽器よりも今日作った楽器のほうがいい。設立40年経ちますが、未だに進歩を止めず、進化し続けるブランドです。その分、どんどん手間暇がかかってきているのですが、このやり方しかできなかったんですよ。
幼稚園の頃から音楽好き スタジオ運営を経てギター職人へ
そもそも音楽との出合いはどのようなものだったのでしょうか?
竹田氏:父親の影響でラジオ番組を幼稚園に入る前から聞いていたんです。この頃から既に洋楽が好きで、「好きな洋楽の番組が聴けなくなるから幼稚園に行きたくない」と駄々をこねていたそうです(笑)
ポール・アンカやニール・セダカなど、はじめはアメリカンポップスを中心に聞いていましたが、中学からはロックも聞くようになり、高校に入るとはじめてギターを買いました。ノーブランドの変わったギターで、秋葉原の楽器店で5000円(笑)。でも当時の自分には十分で、友だちの家の物置をスタジオ代わりにしながらコピーバンドをして楽しんでいましたね。
「好き」を仕事に。その決断に至るまでにはどのような経緯があったのでしょうか。
竹田氏:大学卒業後はレコード会社に行きたいと思っていましたが当時は就職難の時代でなかなか受からず諦めました。結局在学中にアルバイトしていた都内の楽器卸売会社に就職し、フェンダー製品のアフターサービスの仕事を請け負っていました。楽器を納品に行ったり楽器店主催のイベントを手伝ったり。営業の仕事もこなしながら2年ほど働いた後、友人がレンタルスタジオを始めたいというので手伝うことになりました。
ギターの製造を始められたのはいつ頃のことでしょうか。
竹田氏:友人の家族が所有するビルの一角で2部屋の小さなレンタルスタジオを運営する傍ら、受付の裏にあった工房でギターの製作も始めました。前職時代の人脈を生かして必要な資材を仕入れることができたので、この時代に20本ほどのギターを製作していましたね。

そしてラムトリックカンパニーの創業へと続いていくわけですが、独立の経緯についてもお聞かせください。
竹田氏:音楽好きの友人と4人で住み込みしながらスタジオ経営をしていくのは楽しかったし、そこそこお客さんもいました。でも、男4人が食べていけるほど稼ぐのは難しいのが現状でした。
この頃、週に一度某ギターメーカーに通って修理などのアフターサービス業務を請け負っていたのですが、このギターメーカーの従業員たちが当時の経営者に反旗を翻して自分たちで独立しようという動きがあったのです。
それに巻き込まれる形で1983年10月、私と他2名で共同出資し、自社ブランドでギター・ベースの製造販売を手掛ける個人事業主として独立。4年後の1987年に有限会社化、2014年に株式会社化して今に至ります。
生命保険を解約しても、ギター作りは辞めなかった
創業40年以上の歴史を持つラムトリックカンパニー。今に至るまでに特に苦労した時期はありましたか。
竹田氏:立ち上げこそなんとかなりましたが3人分の給料を出すのはそれでも大変で、製造だけでなく修理の仕事も引き受けたり、中古楽器の販売店をオープンしたりして何とか食いつないでいきました。
その後も資金繰りは常に厳しく、知人から引き継いだ高円寺のギターショップは1986年に、高田馬場にオープンしたヴィンテージギターの販売店「シール・ロック」は2000年に知人に譲渡しました。2000年頃は特に経営が厳しく、生命保険を解約して何とか運営資金を捻出したこともあったんですよ。
そんな苦しい日々をどのように乗り越えてこられたのでしょうか?
竹田氏:ギターも好きだし、ギターを作るという作業も好きだったので何とかここまで続けることができました。ギター製造を辞めようと思ったことはありませんね。毎日忙しく楽器を作ったり直したりしているので、目の前のことに必死でそんな余裕もないんです。同業者からはギターを海外で大量生産して安く売るビジネスをやらないかと誘われたこともありますが、それは違うと思って断りました。納得のいかない仕事はしない。それは今も昔も変わりません。
だから相変わらず経営状況は苦しいですし、すごく儲かるわけでもありませんけど、完全に経営に行き詰まることもなくここまで来られたのはお客様や周囲の人々に恵まれていた部分もあったのだろうと思いますね。
そんな竹田社長にとって、これまでで一番の「ハレの日」はどのようなタイミングだったのでしょうか?
竹田氏:1990年頃からギター専門誌でハードウエア系の記事を書くようになりました。そして92年に記録的ロングセラーとなる「エレクトリックギターメカニズム」という本を出版したのです。自分で言うのも何ですが、エレクトリックギター業界ではバイブルと言われています(笑)。
その本をある日本の音楽バンドのマネージャーさんが読んでくれていたようで、ある日「この本を書いてくれた人に、今自分が面倒をみているバンドのメンバーの楽器を作ってもらいたい」と会社に電話がかかってきました。このときにお作りしたのがBUMP OF CHICKENのベーシスト直井由文(なおい・よしふみ)さんのベースだったんです。
メジャー2枚目となるアルバム『ユグドラシル』の制作の少し前で既に有名だった頃だと思いますが、洋楽畑だった私はあまりピンと来ていませんでした(笑)。2002年に連絡をいただき、2003年に楽器をお渡ししましたが、いまだに大切に使ってくれていて、SNSなどでも気に入ってくださっているんだと知ることができてうれしいですね。
今でも「彼らが使っているのと同じ仕様の楽器がほしい」とお声がけをいただくことがたくさんあります。そう考えると、あの仕事を受けた日がその後の仕事を決定づけるハレの日だったんじゃないかなと思います。
今日(取材日)はあいにく梅雨ど真ん中。朝からどんよりとした曇り空です。今日の空を人生に例えると?
竹田氏:この会社を運営していく上での基本でしょうね。ずっと資金繰りに苦労してきたのでピカピカの晴れの日でもないけれど、好きな仕事を続けられているので大雨でもない。雨でもなく、晴れでもない。その中間。そんな空模様だと思います。
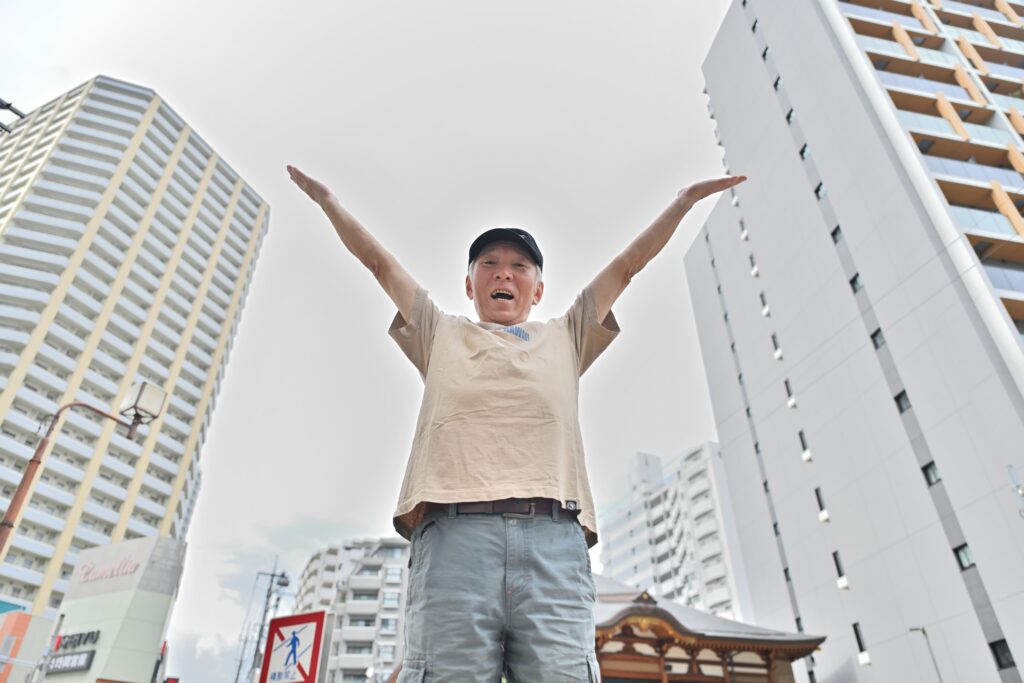
未来のハレを実現するために最も大切にしていること、そして今後の展望についてお聞かせください。
竹田氏:これからもやりたくないことはやらないし、こだわるところはこだわり抜く。どーんと儲かるようなことはこれからもないかもしれませんが、自分らしく、納得のできる楽器作りを続けていけたらと思います。
取材を終えて 撮影小話
大塚:普段なかなか聞けない貴重なお話を聞けてうれしいです。社長のギター愛が伝わってきました! 実は私も音楽好きで、洋楽のレコードなどもたくさん持っているんです。 スマートフォンの待ち受け画面をアメリカのシンガーソングライター、バディ・ホリー氏の写真にしていたら社長に「いいね!」と言ってもらえたことを思い出しました。
竹田氏:大塚さんとはもう6~7年ぐらいの付き合いになりますかね。大塚さんは保険のプロ。頼りになるので、困ったときはまず大塚さんに相談するようにしています。
大塚:ありがとうございます! 工場では社長のお嬢様が働かれていて、技術の伝承にも力を入れられているんですよね。
竹田氏:いや、早く教えて引退したいんだけどね(笑)
大塚:いやいや(笑)。社長にしかできない技術がまだまだあると思うので、これからもそんな社長のお仕事をサポートできたらと思っています! 今日はありがとうございました!

















